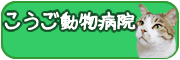何事もタイミングが大事ですね。
その「間」なんですが、これがズレると相手に正しく伝わりません。
お笑いでも絶妙の間がないと笑いは生まれないでしょうし。(間をとる勉強に最適)
間合いというのもあります。お互いの距離感ですね。
遠すぎたり、近すぎたりするとよろしくないです。
「間」が違う、つまり「間違う」と犬のしつけもうまくいかないもの。
犬のしつけの基本ですが、
あなたが教えている事を犬がやろうとした瞬間、意思が見えた時に褒めます。
きちんとできてから褒めるというのでは遅すぎ。
あるいは、近間から遠間へというのが犬のしつけの基本ですが、
間合いが遠すぎるのに呼んでも来るわけありません。
その犬の間合いに入ってから呼ばないと、すぐ確実に来るかどうかなんて土台無理な話しなのです。
次に犬のテンションについて。
物事がうまくいけばテンションはうなぎ上りでしょうが、そうは問屋が卸さないもの。
しつけをしてると必ずテンションが低くなる時がきます。
その時にポ~ンッと飼い主さんがテンションを上げると気持ち切り替えられます。爽やかにやること。
逆に犬のテンションが高すぎてどうにもならない時もありますね。
その時はズズ~ンと飼い主さんがテンションを下げると気持ちが落ち着きます。冷静にやること。
これは間髪いれずにテンションの上げ下げをしないとダメ。(テンションのコントロール)
タイミング的に「それは今でしょ!」と「それ今ですか・・・?」という間の良し悪しが問われるのですね。
最後に、
犬に教えてることがあるのなら、間を置かず連続でやることが大切です。
間を置かないことで緊張感を保ち、一気に仕上げてしまいます。
鉄は熱いうちに打てです。
間を置いてしまうと緊張は解け、だらけてしまうので進歩しづらいのですね。
様々な「間」がありましたが、もう一度みなさん自身で考えてみて下さい!
そうしないと、あっという間に犬は大きくなってしまい、しつけが間に合わなくなりますからね~♪
未分類
上板橋にあるトリミングサロンのハッピースポアさんで定例のトレーニング講習会を行いました!
トリマーさん達が参加してトレーニングを学んでいます。

保護犬のスタンダードプードル、ひら君のトレーニングをしました。
咬みつくのが問題で、しかも大型犬なので緊張感は高まります。
でもまずはリラックスすること♪
犬の気持ちに入り、気を抜かせるのです。
「あれ?この人、何もしないんだ~」と分かれば犬は警戒しませんので。無論咬みません。
大切なのは理想よりも実利と実害。
それよりもっと大切なのは愛情です。
目指すのは調和であり、犬を支配することではありませんね。
犬を尊重しながらトレーニングの可能性と限界を見極めることです。
何だか最近パッとしない・・・ん~、あれもこれも飽きてきてつまらない。
仕事でもプライベートでもマンネリ化って結構やっかいな問題ですよね。
初めはどんなに刺激的だったことも繰り返すことで次第に慣れていき、やがて飽きてしまいます。
同じことの繰り返しがマンネリを生み、毎回続けばいつの間にやらマンネリ化してしまうのですね。
問題なのは、マンネリ化することで思考停止してしまい、無気力になったり、目標を見失ってしまうこと。
しつけにおいてもマンネリ化はあります。
いつも基本トレーニングばっかりやっていると飽きてくるし、退屈してきます。
犬も「はいはい、いつものね」という感じでやるようになり、先を読んで動いたりするものです。
例えば、
野球のピッチャーもカーブとか直球を投げてバッターに球種やコースを読まれないように工夫しますね。
バッターの方もピッチャーの癖を読んで、待ち球を決めたりします。
つまり、読み合いです。
犬のしつけにおいて、こういう読み合いは為されているでしょうか?
次はこれがくるだろう、と犬に読まれていてはあまりうまくいかないものです。
「なぁ~んだまたこのパターンか」「芸がないなぁ」と思われます。
反対に「そうきましたか、斬新ですね」と思わせましょう。
パターン化(順番が同じ)した動きは厳禁ということですね。
すぐ読まれてしまうから、集中する必要もないのです。
まずはパターンに変化をつけることでマンネリ化を防いでみましょう。
歩くとみせかけて、一歩目でフセさせたり。
呼ぶとみせかけて、犬の元に戻ってみたり。
何でも結構なので意識して変化をつけること。「変形」とも言えます。
さて次です。
先程、いつも基本トレーニングばかりでは犬も飽きると書きました。
トレーニングの中身をあれこれ変化つけても、実はそれだけでは不十分です。いつかは必ず飽きてしまうもの。
ならばどうするか?
私ならば遊んでみます!
ピュ~っとあたりを一周走ってみるとか。
プロレス遊びしてみるとか。
これも何でも結構ですからトレーニングとは質を変化させること。つまり「変質」ですね。(遊んでばかりならトレーニングしてみよう)
気分転換にもなりますね。休憩しておやつ食べるのもあり!
最後にもう一つ、
マンネリ化防止の為に常に変化をつけるのですが、どうしても行き詰まることもあるでしょう・・・!
考えても考えても同じようなことを繰り返してしまい自己嫌悪になったり。
そんな時は、自分よりしつけがうまい「あの人」ならどうするだろう?と想像してみましょう。(師匠でも先輩でも友達でもOK)
これはとても勇気付けられます!(へこむこともあるが)
ということで最後の一手は「変身」するということです。これは効きますよ~♪
知性の一つ、判断力の磨き方までお話しました。
次は想像力についてですね。
では続きをどうぞ~!
想像力を磨くには、これははっきり言って、思い切り遊ぶことです!
犬同士の遊びなどで犬社会を学ぶわけですが、どれだけ噛んだら&噛まれたら痛いのかなどを知ります。
遊べば賢くなるのです。
子供の知育玩具というのがありますが、ああいうので大人が想定した遊び方をさせるよりも、(遊びの糸口だけ与えれば充分)
子供が自由な発想で遊ぶことが本当の知育に繋がると思います。(想像力&創造力)
ごっこ遊びとかいいですね~。設定とか一生懸命に考えちゃったりして頭けっこう使いますよね。
ついでなので触れますが、
子供のしつけで教えることに、じゅんばんこ、かわりばんこ、はんぶんこ、などがあります。
他者との協調性を育む狙いがあるわけですが、想像力がないとこういうしつけもなかなか進まないです。
人の痛みや悲しみが想像できないならば順番守る意味も分からないでしょう・・・!
話しが脱線しましたが、
犬の場合、例えば仔犬というのは何を与えてもガジガジ噛みますね?
自由にガジガジさせてやりたい所ですが、そうもいきません。
噛んでいい物といけない物は最初に教えるべきしつけです。
なぜならば、噛むのは遊びでもありますが、本気(危険)にもなり得るからです。もろ刃の剣なんですね。(車の運転と一緒で楽しいが危険でもある)
噛んでいいのは犬用のオモチャだけ。それで遊ぶことが鉄則です。
そして想像力を磨くポイントは「飼い主さんと楽しく遊んだ!」という先行体験を積ませることです。(一人遊びとは区別する)
次回に「あぁ!あの楽しいやつですね!」と前回の体験を想像するようになります。
ボールやフリスビーを見ただけで狂喜乱舞するような♪
でも年がら年中、ボールが床に転がっていたら、現物がそこにあるので想像力もへったくれもありませんね・・・
キーワードは「楽しさ」です。
遊ぶのは楽しい。しつけも楽しい。この人といると楽しい、と思わせたらしめたもの!
イメージ戦略と言えばかっこよすぎですがね。(これも大事)
最後に、
犬というのは私達が思っているよりインテリジェンスです。問題行動の多くはまあ実は分かっててやってます。(その証拠に相手見るはず)
そういう悪知恵が働くのですが、これも知性の一つだから仕方ない。
ただ、知性というのは磨けばさらに光るものです。
知性において犬の一歩、二歩、上を行けるように私達もしつけに有効な知恵を絞りだしましょう~♪
うちの子に知性なんて立派なものあるのかしら?と首を傾げてるあなた!
大丈夫です。全ての犬にはちゃんと知性が備わっています。
悪知恵だって知性のうちですし・・・まあそれをいい方向に向けてあげればOKかと。
もともと持ってる知性をさらに磨いてあげれば犬は今よりもっと賢くなれます!
ではまずは「知性」とはどういうことか考えていきましょう。
「知識」や「知能」など似たような言葉もありますね。
「理性」とか「感性」もあります。
まあ難しく考えないで、ひらたくいきましょう~!
まず理性ですが、犬は動物なので初めは本能しかありません。欲望と言ってもいいでしょう。
人間だって動物ですが道徳教育を受けることで理性を獲得します。
狼少女のように狼に育てられた人間だと狼のように振舞うもの。理性は育った環境や文化、受けた教育によって違ってくるのですね。
ということで理性は知性と同じく考える力のことですがその前提となるのは道徳や道理です。
次に知能です。犬にも知能はありますが人間のそれと比べると低いです。次元が全く違います。
人工知能というのもありますが、人間に近づきはすれど人間にはなれず。
しかし、人工知能の方が優れているのは、知識量や正確性です。計算だって一瞬で出ますね。疲れたりしないし。
いつかは心を獲得し、人間を超えるのか??これはSFの世界ですね~!
さて犬の世界に戻ると、知性とは考える力のことです。
その最高峰は判断力と想像力だと思います。学習や経験から得た知識(知ること)がその基準になる。
感性とは感じる力のこと。味わう力であり、表現する力とも言えます。これも非常に奥深いものですが今回はパスします。
では言葉の意味はこれくらいにして、犬の知性を磨くには?という本題に入っていきましょう。
まずは判断力から。
キーワードは「制限」です。
例えば、あなたにお金が無限にあったとしたら、使い道は何も考えずに好きな物を好きなだけ買うでしょう。
羨ましい話しではありますがこれではいけません。限られたお金の中で何が必要かを考えた上で買うから知性が磨かれるのです。
そこに「判断」が存在します。その買い物が成功でも失敗でも判断力は磨かれていくのです。(失敗したら勉強代になる)
犬に制限をかけ、イエス・ノーの2択の問題を出すことで判断力を磨いていくのが最も簡単な方法でしょう。
例えば、
一本の線を地面に引きます。これを先に超えるのはあなたか犬か?
これがテストだとして、正解はあなたが先に超える、だとしたらこの超簡単な2択問題で正解できるでしょうか!?
ポイントは制限をかけるということ。ただ問題を出すこととは違います。
①時間的制限
今日中、一週間以内、一ヶ月以内、一年以内など、問題クリアの期限を設定すること。
②空間的制限
線を超える距離を50cm、40cm、30cm、20cm、10cm・・・と狭めていく目標を設定すること。
③方法的制限
リードやおやつなどの道具を使う、少し使う、全く使わない、など道具の使用制限を設定すること。
まあこんな感じです。レベルに応じて制限を強めるか緩和させるか決めましょう。
犬への制限であると同時に自分への制限でもあるので、自らを律することが犬を律することに繋がります。(これ大事)
犬の方は問題をクリアし、制限を解除されれば、より自由を手に入れていく仕組みです。
無限のチャンス&初めから完全に自由では、犬は知性など磨く必要性も必然性もありません。
制限の絶妙な調整こそが犬の知性を磨くコツなのですね~♪
今日はここまでとします。続きはまた明日!
パラドックスとは逆説、逆理などと訳されます。
命題があって、それを紐解くと、受け入れがたい結果が出てしまう。(単なる矛盾とは違い真理である)
ネットで調べれば色んな例が出てきますが、分かりやすいのだと、
「クレタ人はうそつきであるとクレタ人が言った」というパラドックスがあります。
①もし本当にクレタ人がうそつきなら、このクレタ人は正直にうそつきだと言っているのでうそつきではなくなる。
②もし本当にクレタ人がうそつきではないのなら、このクレタ人はうそを言っていることになる。
こういう無限ループが続くのがパラドックスです。
もう一つはダチョウ倶楽部さんのネタから。
「絶対に押すなよ」です。あの熱湯風呂のやつ。
態度、態勢としては「押してくれ」と言ってるのに、口では「絶対に押すなよ」と。
お約束で押されるのですが、オチが分かっていても安定して面白い!
しつけにおいてのパラドックスに、この「押すなよ」系統のものなら無数にありますね。
口では「~~」と言っているが、態度は「~~」と言っている的な。
くどくなるので書くのは遠慮しますが、要するにしつけで大事なのは言葉ではなく、態度・行動ということ。
もう一ついっときましょう。
竹原ピストルさんの名曲「よーそこの若いの」のサビです。
「よーそこの若いの、俺の言う事を聞いてくれ。俺を含め、誰の言う事も聞くなよ」
こういう表現方法は面白いですね。理屈を超えて「自分らしく生きろ」という熱い気持ちが伝わってくる気がします。
しつけにそのまま置き換えると、
「よーそこの犬よ、俺の言う事を聞いてくれ。俺を含め、誰の言う事も聞くなよ」
私なりに解釈すると、
①言う事を聞いてほしいのはまず間違いないでしょう。
②しかし、言う事を聞かない部分も可愛いと思えてしまう。(愛嬌という)
一見、矛盾しているようですが、両方とも真理なのでパラドックスなのですね。
この問題を解決するには、
犬の成り立ちを考えることです。(参考:砂山のパラドックスの履歴現象と同じ)
狼から始まり、家畜化されて、使役されて、現在の愛玩犬にまで至ります。
もし犬が言う事をきかなかったのなら、使役できないし、家畜化もされなかったでしょう。
なので犬は本来は言う事を聞くものと思い定めること。それが犬の定義とします。
この決め事から出発すれば、道が大きくそれることはないはず。
犬が言う事を聞くべきなのか、聞くべきではないのか、この答えは、その成り立ちが関与しているということですね。
最後に、言う事を聞かせたいのに全然聞いてくれない!と嘆いてる飼い主さんは、
「急がば回れ」のことわざ(パラドックス)の通り、遠回りに見えても確実な道を行くことですよ♪
フォローの形を進化させるのはいいけど、一体どうやってやるのでしょう?(フォローはサポートやアシストに置き換えてもOK)
より小さく、見えにくい、さりげないフォローは難しいもの。必要最小限の過不足ないフォローができたら最高なのですが。
より大きく、あからさまな、わざとらしいフォローはありがた迷惑になりがち。過保護、過干渉などの過剰なフォローは避けたいもの。
トイレの例だと、フォローの形としては「粗相の後処理」か「適切なトイレのしつけをする」かの違いですが、
適切なトイレのしつけには段階があります。
①ハウスからトイレへ誘導
②部屋に放している時にトイレへ誘導
③犬自らトイレへ行くようになる
ざっくり言うとこんな感じですが、よくある失敗は、
フォローが足りないケース→いきなり③を犬に期待してしまう。
フォローが過剰なケース→失敗を防ぐだけの目的でハウスに入れっぱなし。
無理なくしっかりと段階踏んで進化していくことが大切です。
あと、「間違ったから・失敗したから」当たり前のように注意するというのはダメ。心の中で思うだけでもバレるのでダメです。
むしろ勇敢に挑戦した上での失敗ならばフォローすべきです!今のは仕方ない、気にするな、ドンマイと心の中で思えばよし。
何故間違ったのか?どのような性質の失敗か?を考えることが大切なんです。
それによってフォローの形をまた変化させる。そして犬の方もトライ&エラーを繰り返して成長していく。
そしてまたフィードバックして・・・この繰り返し。
叱り飛ばすだけでは犬はついてきません。悪いと分かっている犬に対しては、叱る必要ないのですね。ただリトライするだけでOK!
そういう絶妙なフォローをされると、あぁこの人はよく分かってくれている!と犬も感動し、感謝します。
最後に、フォローの反対は邪魔することです。
助けるどころか足を引っ張ってしまってることもあります・・・グイグイと。
しつけとは真逆の考え方ですが、トイレの例で言うと、
①ハウスに入れっぱなしや鎖で繋ぎっぱなしでトイレへ行けなくする
②部屋に放してトイレ場所を特定しづらくさせる
③犬自らトイレへ行こうとしたらひき止める(同居犬など)
これはウソみたいですが実際にはけっこう普通に起こっていることばかりです。
誰も邪魔しよう等とは思ってはいないでしょうが、遊ぶつもりやフォローのつもりが結果的に邪魔になってしまうこともあるのですね。
そして教育熱心になればなる程、教えることばかりに目がいき、フォローが疎かになりがちです。
何もしない、何も求めない、素直になること。
ただ話しをするとか、そばにいる、そういうのだけでも意外とフォローになったり、癒しになったりするものですよ♪
いきなりですが、犬って癒されますよね~♪
人間のように口答えしませんし・・・
何も求めず、ただじっとそばにいてくれる。
あ、もちろん逆に元気に騒いでるような時もそれはそれで癒されますね!
さて、そんな癒しの存在である犬ですが、
犬にとって私たちは癒しになっているでしょうか?
もし、あなたの愛犬が何か困っているならば手を差し伸べて助けてあげたいですよね?そしてできれば癒してやりたい。
癒せるかどうかまでは分かりませんが、今回はそういう「犬へのフォロー」のお話です。
フォローとは、補い助けるという意味ですが、犬の何を補い、どんなことを助けるのか?
例えば、
愛犬がなかなかトイレを覚えないとします。毎日部屋のいたるところで粗相してしまうのです。
これ実は困るのは飼い主さんだけであって、犬はちっとも困ったりしていません。
出る物ところ構わずの精神で、景気よく出してむしろ快感・・・!?
ちょっと汚い話でしたが、犬には本来、トイレのしつけなんて必要ないということです。
しかーし!それは飼い主さんとしては絶対に困ること!だからしつけを受けてね、ということです。
ぶっちゃけ人間の都合です。しつけとは。(人間と暮らすから必要なもの)
病気の治療だって、美容室でシャンプーするのだって、全部そう。
犬自身が治療したくて病院行ってるわけではないし、野生動物ならシャンプーなど一生に一回もしません。
全て飼い主さんの意向で決定されるのですね。
誤解しないでほしいのですがそれが悪いというのではなく、
「しつけ」「治療」「シャンプー」などをすることが、必ずしもそのまま犬へのフォローになるわけではないということです。
最も深刻なのは、病気の治療ですね。特に命に関わるような。
飼い主さんが考えること、望むことは、病気からの快復のみでしょう。
快復の見込みがあるのならそこに賭けたいのですが、治療も楽なものばかりではありませんから色々と悩むのですね。
ましてや快復の見込みがうすい場合、治療ではなく、痛みの緩和などを目的とした「ケア」へ考え方はシフトするかもしれません。
端的に言うと、この場合「治療」か「ケア」か、フォローの形は変わるのです。
シャンプーの場合はどうでしょうか?
嫌がる犬を無理やり週一回ペースで洗う。ひどいケースだと毎日洗う。これはやはり犬にとってはストレスでしょう。
何故嫌がるのかを突き止めて慣れさせる練習をするとか、せめて月一、二回ペースにするとか、犬への配慮がほしいものです。
フォローの形としては「シャンプーをする」か「シャンプーのやり方を変える」かの違いです。
最後にしつけはどうでしょう?
前述のトイレのしつけですが、毎日のように粗相されると飼い主さんもやはり困ります。
困ってるというのは犬も分かるものです。あなたが不機嫌なのはすぐ分かる・・・!
明るく掃除をして下さいとは言いません!ただ、トイレ場所を指定してあげたら両方丸くおさまるのでは?と思うのです。
初めのうちはトイレ場所を指定するためにサークルを使うとか、2時間置きにトイレ連れていくとか、手間がかかるものです。
ポイントは「うちの子はどの程度のフォロー(助け)が必要なのか」を考えることですね。
フォローが足りないと結果的にフォローに追われるようになります。尻拭い的な。
言わば、フォローも進化させるべきものなのですね。
今日はここまで。続きはまた明日です!
「しつけの主導権」とはおかしな言葉です。
本来、しつけというのは親が子に対して行うものなので主導権も何も考える隙間もないほど決定してるはずですから。
しかし、犬の場合は話が別です!
なぜか立場があべこべになったりするのですね。
つまり、しつけられるべきはずの犬の方が主導権をとり、しつける側の飼い主さんが犬に従っているという構図です。
原因はまあ色々なんでしょうが、犬はただ可愛いだけの生き物ではないのは確かかと。
オオカミの時代から受け継がれている爪と牙は今も健在!
場合によっては一触即発の事態にもなりかねません。
事が起きてからでは遅いので、トラブルに先んじて愛犬のしつけはしっかりとしておきましょう、というのが私の主張。
さて、主導権の話しですが、
例えば、
サッカーだと相手チームとボールをとりあいますね。
ボールを持っている方が主導権をとっています。
シュートを打つことも可能になるわけですが、まだゴールを決めたわけではありません。
でもまずはボールをとることが先決です。「ボール」=「主導権」をとらないとゴールを目指せないのですから。
もしかして、ず~っと相手(犬)ボールになってませんか??
あと、ボール支配率(ボールを持ってる時間の割合)が高ければ勝てる確率も高くなるのが理屈ですが、
現実はそうなるとも限らないのが面白いところ。ボールを一瞬で奪われて一気にカウンターでゴール決められて負けたりします。
主導権はその時々で移り変わるものなんですね。
さて、犬のしつけの場合だと目に見えるボールのようなものはありませんが、どうすれば主導権をとったと言えるのでしょうか?
答えは簡単!
あなたの前に犬が出ていたら主導権とられてます。
あなたを見ようとしないなら主導権とられてます。
これは「歩行」で改善できます。歩くことで主導権を取り返しましょう。
歩く「位置」はどこがいいのか、「誰」と歩いているのかを教えてあげるのですね。
犬がまるで一人で歩いてるような感じで好きなようにを臭いかいだりマーキングしたりしながら歩いている。飼い主さんはそれについていく。
これをサッカーで例えると、相手がドリブルしてくるのを止めるどころか後ろからついていって、ゴール決められるのを見守っているようなものです。
これではほとんどオウンゴールのようなもの・・・ゲームになりませんね!
しかし、犬のしつけはゲームではないし、勝つためにやるわけではない!と反論があったとします。
要するに、何のためにしつけをするのか?という疑問です。
これはやっぱり勝つためなんですよ。犬にではなく、自分にです。
幸せも夢も犬のしつけも自分で掴みとるものではないでしょうか。(しつけは犬と力を合わせてね)
負け試合というのがありますが、負けると分かっていても初めから諦めてるのと、挑戦するのとではその後に大きな差が出ます。
戦略的な捨て試合とかは全く別の話しで、基本的には勝ちに行く姿勢が大切なんだと思います。
犬のしつけも負け試合のような気持ちだと主導権はとれません。
主導権をとる!という気を持ちながら、勝つための戦略(しつけ)を学べば必ず良い結果が出るはずです。
さあみんなで勝ちにいきましょう~♪