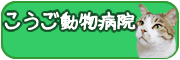本音とは裏腹に行動してしまう・・・
わざと言う事に逆らってしまう・・・
そんな天邪鬼な性格を犬も持っているでしょうか?
天邪鬼をすご~く悪い意味で解釈すると犬にはあてはまらないと思いますが、(悪意でおとしめるような)
「何かをおすすめされると嫌になるけど、禁止されるとつい手を出したくなる・・・!」
私達も理屈ではなく、こういう部分がありますね。犬にもこれはあると思います。
別にわざと逆らってるわけではないのですが、何となく気がすすまないとか、
ダメと言われると何故だか興味をそそられる、みたいな。(不思議ですね~)
例えば、
ごはんを食べない犬の場合、
飼い主さんは心配のあまりあれやこれやとトッピングを試みます。(チーズやささみとか)
それでも食べてくれないと手で食べさせてやったりと至れり尽くせり。
終いにはごはんは常に置いておくという始末・・・
「食べさせよう、食べさせよう」とおすすめすればする程、犬は食事が嫌になります。
老犬を除いて健康な犬ならば、普通はすぐ食べます。食べないのはお腹が減ってないか、ストレスでしょう。(無理やり食べさせられるという?)
そんな場合は、思い切って一回、食事を抜いてみてください!
禁止されればそそられるのです。単純にお腹もすきますし。(これでも食べないならば何かしらのストレスが原因でしょう)
押してもダメなら引いてみる。押しの一手だけでは問題は解決されないのです。
先程の例だと、ごはんをすぐに食べられた→ご褒美としてチーズをあげる、この方が理に適ってますね。
次に、人(犬)のものが欲しくなる天邪鬼さんもいます。
例えば、
多頭飼育の場合、犬同士で遊んでいても結局ひとつのオモチャを取り合ってしまうものです。(各々のオモチャはあるのに!)
これはオモチャそのものに絶対的価値があるのではなく、相手がいて新たな価値が生まれるわけですね。(競争して勝ちたい)
だからわざと嫌がらせでそうしてるわけではなくて、この子とこの子の場合はこうなるという受け止め方をしましょう。
要するに相性の問題です。まあ別々で遊ばせてもいいわけですし、オモチャを使わない遊び方に変えれば一緒に遊べるかもしれませんし。
「人のもの」という禁止事項が欲しくなる原因なのです。
「あなたのもの」というおすすめ事項はノーサンキューの場合もあるということです。
節度なくべたべた撫でてやるのはノーサンキューであり、適度に離れる時間があるから共に過ごす時間が有難く感じるのです。
天邪鬼という心理があるということを頭の片隅に入れておくとトレーニングの時にも役立つかもしれませんよ♪
未分類
主従関係と言うとちょっと抵抗感ある方も多いかもしれませんね。
しかし初めに押さえておかなければいけない前提として、犬は主従関係でしか従うことはありません!
犬は犬であり、人は人であります。どちらかが主人になるしか共存の道はありません。(その上で限りなく対等に友達親子みたいになればOK)
毎年ニュースになるような悲しい事故が起きてしまいますが、例えば家族の誰かが愛犬に噛まれたらどうしますか?
どれだけ愛犬が可愛くても優先されるべきは基本的には人です。(人に過失や責任がある場合もあるが)
何故そんなことになったのか・・・真剣に考える必要があるでしょう。
主従関係の他にも上下関係や信頼関係など、犬のしつけに関連する言葉がありますね。
まず主従関係ですが普通に解釈すると、「主人と従者の関係」です。
あなたと愛犬のどちらが主人か??がポイントとなります。
愛犬がご機嫌ななめの時には唸るとか、眠い時は怒りっぽいとか・・・!
これはそのことを正当化する理由になりません。
これこそが主従関係の現れであり、今いる位置です。
一応、上下関係はあるのかも(ないかも?)しれませんが、主人には成りきれてません。
普段はいい子だとしても、いざとなれば逆らうのは「従者同士の上下関係」に過ぎないのです。
主人とはあちら側であり、従者とはこちら側です。
家族全員が主人になるべきです。明確な順位付けはさておき「言う事を聞くか・聞かないか」が判断基準です。
すごくシンプルなのです。例外はありませんよ~!
次に信頼関係についてです。
これは「お互いを信じ合う関係」ということですね。
主従関係とは別系統で、信頼関係は存在します。主人でも従者でも、上でも下でも構いません。
「信頼するか・しないか」の関係です。
言う事を聞くかどうかは別として愛犬を信頼するならば、それはそれで素晴らしいことだと思います。
ただ、「飼い主さんが我慢して過ごすような日々」は望ましくはありません。
望むべきことは、
「お互いに信頼し合い、健全な主従関係を築くこと」です。
愛犬はあなたのことを信頼してくれてますか?
信頼とは「お互いに信じて頼り合うこと」です。一方通行ではなく、双方向なのですね。
あなたは愛犬のことを守ってばかりではないですか?
たまには頼ってもいいのですよ、お互い様ですから。(言う事を聞いてくれたらどんなに助かるか!)
最後にまとめますと、
信頼関係は信じて頼るか否か、あなたと愛犬の双方向のやり取りである。(精神的・理想的)
主従関係は従うか否か、ただそれだけのシンプルなやり取りである。(身体的・現実的)
理想の飼い主像は、
「愛犬を信じて頼る。愛犬に信じられて頼られたらちゃんと応えてあげる人」です。
これがすなわち健全な主従関係なのです。
回り続けるコマのように、主従関係はバランスが大切です。(コマを回すのはあなただが、コマは犬である)
軸がぶれればコマはあっという間にバランスを崩し、止まってしまいます。
えらぶったり、反対にへりくだったりするのは簡単ですが・・・
信頼のもとに(コマは回ると信じる)、バランスをとりながら(コマを回す技術)、
主従関係とはどう在るべきかを追求する姿勢(絶えず挑戦すること)が求められるのだと思います。
あなたなりに「主従関係」と向き合って頂ければ幸いです♪
国語には読み、書き、話す、聞く、の4つがありますね。
はてさて、我らが犬語はどうでしょうか?
読み→文字がないのでなし
書き→同上(なし)
話す→言語ではないがある
聞く→同上(ある)
普通に考えるとこうなります。
しかし、例えばマーキングはどうでしょうか?
電柱などにおしっこをかけて縄張りを主張するというあれです。
これ、もしかしたら「書き」にあたるかもしれません。
ということは犬が地面を嗅ぐ行為は「読み」なのでしょう。
ん~、まだまだありそうですね。
救急車のサイレンに反応して、つまり「聞く」そして、遠吠えするのは「話す」でしょう。仲間を呼んだりする時の名残ですね。
犬語が少しずつ分かってきましたね。
もしかしたらチャイムの音に反応して吠えるのも・・・そうですね、「聞く・話す」にあたります。
では、
散歩中に前から歩いてくる他犬に向かって吠えるのは何にあたるでしょうか?
何だか・・・どれもあたらない気がしますね。
私の意見ですが、これは「見る」「感じる」にあたると思います。
私達でいうと手話に似てるかもしれません。ジェスチャーや表情を見て感じるのです。
さて、普段犬は飼い主さんの何を見て、何を感じているのでしょうか??
それがそのものズバリ!行動に反映されてくるわけですが・・・!
まずここまでよろしいですね。犬語は「見る」「感じる」がポイントです。
ここからはちょっと視点を変えてみましょう。
マーキングの話に戻ります。
例えば、あなたがコンビニに行ったとして、ガムを買ったとしましょう。
「テープでよろしいですか?」と必ず聞かれます。(エコの為)
「袋ください」とは言いづらい・・・じゃなくてそれは今はどうでもいいのですが、このテープ!
これはマーキングの一種です。購入済みというね。
業者との契約書にハンコを押すのだってマーキングの親戚みたいなもんです。
愛犬があなたの足や、お家のいたる所にマーキングするとしたらそれは、
「自分の所有物である」というニュアンスがあります。(あなたのハンコをだれかの額に押すようなイメージ)
決して良い意味ではありませんが、絶対に即やめさせなければならないという程の問題でもありません。
マウンティングなんかも同じですが、これらはコミュニケーションのひとつとして受け取り、
「総合的に判断して対処すること」が大切です。まあ、私なら様子見てたぶんやめさせますがね。
では、続きまして
同じくコンビニに行ったとして、店員さんが
「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」と挨拶してくれました。
何となくでいいのですが、
「感じがいい店」「感じの悪い店」という違いを経験されたことはないでしょうか?
はい、これは挨拶の感じによります。
「真心がこもってる感じ」と「ぶっきらぼうな感じ」だとどっちがいいかは聞くまでもありませんね。
さて、愛犬はあなたの普段の「声の調子」をどう聞いているでしょうか?
愛犬が吠えてるからなだめようと「大丈夫、大丈夫よ」と真心をこめて声をかけたら余計に吠える場合、
これは、「吠えたから褒められた」と愛犬が受け取っている可能性があります。真心を込めてる(なだめる)のが仇となるパターンです。
声に感情をこめるのは大切ですが、それがどう伝わっているかということもよく観察しましょう。
それでは最後ですが、
またもやコンビニに行ったとして、店員さんの身だしなみが整ってなかったり、店員さんがポケットに手を入れてたりしたら、
あなたはどう見て、どう感じますか?
感じ悪い店だな・・・もう二度と来ないぞ、と思われても仕方ないですね。(自分が客として大切に扱われてないと感じる為です)
翻って、 愛犬はどんな所であなたが上か下かを判断するのでしょうか?
大きな要因として、「姿勢」があります。指示を出す時に猫背はダメです。威厳がなくなりますし、犬から見たら懇願になります。
「お願いだから、頼むから・・・言う事聞いてね」という下手に出る態度は犬には通じませんし、むしろ逆効果です。
「見た目で判断される」というのが犬語の現実なのです。心がどれだけ清くて高尚だろうが、犬には「弱さ」としか映りません。
人間相手ではありませんから、そこをはき違えてはいけないのですね。
「継続は力なり」と言いますが悪い方向にもそれはあてはまります。
他犬を見て毎日のように吠えていた犬は条件反射で「吠えてしまわざるを得ない犬」になってしまいます。(見ただけで吠える犬の完成)
頼むから吠えないでちょうだい!という懇願は「私を守ってね、それ吠えろ」という意味に解釈されるということを自覚すべきです。
犬語は見た目が9割なのです。(だって手話と同じようなものだから。心の中はミエナイ)
一例を記します。歩き方、リードの持ち方、姿勢、表情、触り方、動きのスピード、ハンドサイン、オモチャや食べ物の見せ方、与え方など。
吠えた時のあなたの慌てた様子、うなった時のあなたの怯んだ様子、追いかけたら子供が逃げる様子・・・など。
全てぜ~んぶ見られてます!(総合的に判断し、あなたではなく犬が家族の順位を決める)
逆に言えば飼い主さんも犬の様子を見てないとダメということですね。
あれ?最近イタズラがすぎるな・・・、言う事聞かなくなってきたかな?と思ったら要注意ですよ~!
はい、当然感じるでしょう。
特に今までけっこう好き勝手やってきた犬にとっては物凄いストレスでしょう・・・!
それは仕方ありません。しつけをするならば一緒に乗り越えるしかありません。
大切なのは、
「ストレスだからやらない」ではなく、「最小限のストレスに留めるにはどうしたらいいか」です。
やるか、やらないか、で迷っていたら・・・うまくいくものもいかないのではないでしょうか?
さて、ではストレスを最小限にするにはどうするか?ですが、
その前にまず、突然しつけを始めるという事は犬の立場からしたら、
「今までの暮らしは何だったの??急に何ですか??」となります。(私達で言うと法律が180度変わるようなもの)
このように戸惑うのは当たり前ですね。
例えば今までは部屋で好きなように居場所を決めて、行動(吠えまくる)してた犬が、
ある日突然、ハウスに入れられて、行動を制限されるわけです!
ストレスですし苦痛ですね・・・
それでも頑張ってみたい!という方は覚悟を決めましょう。
簡単には直りません。
たぶん思っているより、2倍~10倍は大変です。(大げさではなく)
例えるならば私たちが英語やフランス語を習うとして、
1回とか2回のレッスンでしゃべれるようになりますか?普通はならないでしょう。(単語は覚えられるけど)
しつけとは犬との会話であります。
つまり犬語を習うようなもの。
しかも言語ではなく、実技を伴う会話方法です。(詳しくは次回にふれます)
英語ペラペラになるのは半年後か、1年後か2年後か分かりませんが、それくらい大変なことなのです。
ではそれはいいとして、
犬のストレスを減らすにはどうするか?ですが、
これは結局のところ「飼い主さんが早く犬語をマスターする」しかありません!(すいません、これしかないのです)
注意してほしいのは、
「飼い主さんが良かれと思ってやってることが実は愛犬にとって悪影響を及ぼすこともあり得る」という点です。
ご飯を欲しがるだけ与えれば当然、肥満になりやすく、病気になりやすくなります。
病気になったら病院に連れて行くのは当たり前ですし、簡単ですが・・・
そうならないように予防するのが本当の愛情ではないでしょうか。
しつけも問題が起こってから直すのでは愛犬に余計なストレスがかかります。
ですから理想を言えば、まず飼い主さんが犬語をマスターする、次に犬を飼う、という順番がいいですね。(現実的には同時進行ですが)
ちなみにストレスは伝染します。
愛犬の問題行動を自分が我慢すればいいと思っている飼い主さんは、ストレスを感じているはずです。
そんな飼い主さんを見て、愛犬もストレスを感じずにはいられません。
日々のすれ違いからやがて軋轢が生じて家庭不和が・・・つまり、しつけしてもしなくても、どっち道ストレスからは逃れられない?かも。
でも、朝起きて布団から出る時みたいに「嫌だなぁ」と思ってもたいていは乗り越えていく、それがいわゆるストレス。
なかなか乗り越えられないような劣等感とか、そういう本物のストレスはもちろん別として。
犬のしつけに限ればそんなに大層なものはありません。ちゃんと勉強すればしつけは誰でもできますし、乗り越えられるレベルのストレスです。
愛犬を過小評価せず信じてあげることが大切だと思いますよ♪
昨日の続きで今回で完結となります。
さあ、うまくリードできない第二の原因とは・・・!
それは「感情を正しく読み取れてないこと」です。
犬はあなたとの散歩を楽しんでますか?そう見えたとしても、もしかしたら・・・
「においを嗅ぎたい欲求」「突き進みたい欲求」があるに過ぎないのかもしれません。
仮に、「実は自分の欲求を通してるだけ」であれば・・・!言うことを聞かない犬になって当然ですね。
他方で人間の世界でも野生動物の世界でもいじめはあります。
遊びで粉飾されたいじめもありますね。
遊びから喧嘩に発展することもありますね。
いじめっ子は遊んでいたと言い、被害者はいじめられていると思っている。
「いや、遊んでいただけだよ」といういじめっ子の言い分は私には通用しません。
本当に犬は散歩を楽しんでいるのか?本当にいじめっ子は遊んでいただけなのか?これは全然違う話ですがリンクする部分もあります。
犬の散歩のみならず愛犬との生活全般をここらでちょっと一回考え直してみませんか?
愛犬を正しくリードしなければいけないということを意識してみませんか?
そうじゃないとお互いにすれ違う結果になりやすいのです。
優しく手をひくはずが、逆に激しく引っ張られる結果になります・・・!
もちろん子供と犬は全然違いますがね。参考にはなりますよ。
前向きに頑張れば・・・必ず引っ張り上げてくれる人との出会いがあるでしょう。(腐らない、開き直らないで求め続けること)
自分自身がリードされて初めて、リードするとはどういうことかを学べるのです。(愛されて愛を知るのと同じ!)
結論、犬によってリードの仕方が違うように、「飼い主さんによっても正しいリードの仕方は違います」(よって実技でしか指導不可能)
あなたの感性に最も響くやり方を選択しましょう♪
犬によってリードの仕方は違う。
やり方は合っていてもしっかり実行できていないのがリードできない原因かも・・・という所までお話しましたね。
では今日は続きをお聞き下さい!
例えば、
2、3歳の小さな子供と手をつないでるのをイメージしてください。
その子を家から公園まで連れて行きましょう。
さて、まず相手は小さな子供ですね。まだ一人では公園に行けないので案内と見守りが必要です。(相手を知る)
感情を読んでみますと、笑顔で楽しそう♪とても喜んでいます。(感情を読む)
適切なリードですが、声掛けはどうしますか?姿勢は?表情は?手をひいて歩くスピードは?(適切なリード)
私ならば低い姿勢で笑顔で優しく声をかけ、ゆっくり手をひいて歩きます→寄り道もするでしょうが公園まで何とかつく。(結果に繋ぐ)
これはだいたいみんな似たり寄ったりの答えかと思います。
では次に、愛犬との散歩の場面を思い出してください。
・・・核心を突きますが、
一体どちらがリードしてますか??
「私です」という方、素晴らしいことです!
「犬です」という方、直りますから諦めないでくださ~い!
何故こうなるか?疑問ですよね。
子供と同じような「優しい扱い方」をしてるはずなのに何故うまくいかないのか?
これは以前「犬は家族か?12/8」の回でお話させて頂いたように、
「犬は犬である」という視点が欠如していることが主な原因です。犬という生物の習性や本能を知ることが大切。
二番目の原因は・・・今日はここまでにしておきましょう。
続きはまた明日です。
犬のしつけにはまず集中、つまりアイコンタクトが大切でしたね。
集中なくしてしつけは絶対にうまくいきません!
論より証拠、周りを見渡すと、そんな実例がゴロゴロしてませんか?
飼い主さんの言うことよりも地面のにおいかぎに忙しい犬。(地面に集中)
ご飯の時は言うこと聞くけど他は一切言うこと聞かない犬。(ご飯に集中してるだけ)
ダメと言っても甘噛みしまくる犬。吠えまくる犬などなど・・・!(その対象物に集中)
それは主従関係ができてないからですよ、そもそも言うこと聞く気持ちもないのですよ、まずは飼い主さんの存在を認めさせましょう、
と、これまでも言ってきたと思いますが、残念ながら具体的には実技じゃないと伝えることは不可能です。
何故ならば、犬のしつけは「感性」だからです。
プログラムされたロボットと違って、犬は生き物なので本能や感情があります。
犬のしつけに、こうしたら、こうなる、という絶対的な方程式はないわけですね。
だから犬という生き物を知り、感情を読み取り、適切なリード(プロセス)があって、アイコンに至るわけです。
そしてまたアイコンから始まってまたアイコンで終わる・・・これの繰り返しでしつけが進んでいきます。(アイコンは原点であり頂点)
では正しいリードの仕方とは?
はい、もうお分かりのように犬によって違います。
しつけ本を読んでこう書いてあるからとか、しつけ方法を友達から聞いたとか・・・!
なかなかうまくいかないのはきっと、
①そもそもやり方がその犬に合ってない。
②やり方が合ってても正しく実行できていない。
このどちらかでしょう。(犬が悪いということは普通あり得ません)
今回は①は除外して、②の場合を解説します。
基本的な流れは、まず相手を知り、感情を読み、適切にリードして、結果に繋げる、です。
内容が複雑なので今日はここまで。
続きはまた明日!
叱り方に続いて、今回は褒め方のお話です。
同じパターンで考えると、
褒める時は喜びの感情が伴う。
喜びの大小が相手に伝わるか影響する。
ここまではOKですね?
「叱る・怒る」と「褒める・喜ぶ」の図式になります。
叱り方の注意点として怒りすぎると相手の為(指導)にならずただの感情爆発になる恐れがあったのですが、
喜びすぎるとどうなるでしょうか?
これは、
全然問題ありません!褒めることと喜ぶことはほぼ同義語だと考えます。(褒め自体の弊害はない)
「愛犬が喜べばあなたも嬉しい」
ということはたぶん、
「あなたが喜べば愛犬も嬉しい」でしょう。
「愛犬が幸せならあなたも幸せ」ならば「あなたが幸せなら愛犬も幸せ」かなと思います。(ぜひ直接聞いてみたい)
ただし・・・!
喜びの押し売りはいけません。
褒めの押しつけはいけません。
これは順番が大切ということです。つまり、まず犬、そして飼い主さんです。
犬が喜ぶことが最初であり、次にあなたが喜ぶのがしつけにおいての正しい褒め方です。
例えば、
無理やり力づくでオスワリさせたのに、あなたが嬉しいから、「よーしよし」と褒められても、犬は全然嬉しくありません。
正しくは、
犬が興味をもつやり方でオスワリの形に導き、褒める&喜ぶ。
一番初めだけは犬は必ずしも喜んでいないかもしれませんが、まずは「楽しんでもらえるやり方」を意識しましょう。
これが基本です。
そうしたらそのうち、あなたに喜んでほしいから犬が自らすすんで座るようになります!(スムーズに座るようになる)
これはトレーニングを楽しんでいる状態です。「楽しみ~喜び」へシフトしていくのですね。
犬→あなた→犬→あなた・・・と「喜びのキャッチボール」ができてきたら健全な主従関係の形と言えます。
もう一度言いますが、まずは犬を喜ばすことです。何かして欲しいならばまずは与えよ、です。(厳密には楽しみ→喜び)
すぐ思いつくのは食べ物とかオモチャですね。
確かにこれは喜ぶ犬が多いですが、あまりにも即物的なため、飼い主さんへの尊敬や感謝が得られない恐れがあります。
要するに食べ物がほしいから従うにすぎない犬に育つかもしれないということです。
食べ物は強力すぎるが故に使い方が難しいですよ、というのが私の意見です。(私達も働かないで給料がでたらどうなるか?)
ではどうするか?正しい褒め方とは?
言葉で褒めるやり方は感情表現が豊かな人に向いてる褒め方です。
感情をこめて、抑揚をつけ、上がり調子で褒めましょう。もちろん笑顔です。
普通に語りかけるだけでも犬は嬉しいかもしれません。
相手にされている、大切にされているという自然な喜びへと繋がると理想的です。
次に触って褒める、撫でてやる方法です。
どこを触ればいいですか?とよく聞かれますが、
「どこでもOK」が答えです。部位よりも触り方が重要です。(じゃあ目でもいいのね、とか意地悪な解釈はやめてね)
やさしく撫でる、パンッと触る、ぐしゃぐしゃに触る、どれがいいのかはその場面によります。
ほんの一例ですが(もちろん例外もあります)
やさしく撫でるのはリラックスさせるので待つ練習に向いてます。
パンッと触るのは緊張感を維持できるので歩行練習に向いてます。
ぐしゃぐしゃに触るのは高揚感を与えるので遊びの時に向いてます。
最後に食べ物やオモチャを与える方法ですが・・・やはり使い方が難しいので下手に多用しない方が良いでしょう。
最悪の場合、褒めたくない行動を褒めてしまっている場合があります。
典型的なのはオスワリしたけどおやつあげる時には飛びついている、みたいな。
最後に、どの褒め方にも共通するのはタイミングとサプライズが重要ということです。
現象を捉えて3秒以内に褒める!意外性を意識する!
大量の、分かりきった、形だけの褒めは犬もしらけるものです。
サプライズのプレゼントって嬉しいですよね?毎回じゃなくていいから「え!まさか」というのがいいんですよ♪
これが一番苦手という方が多いでしょう。
犬を叱ることは「かわいそう」であり、できればしたくないですね。
しかし、しつけとして「ダメなことはダメ」と叱らなくてはいけないのも頷ける。
皆さんここで葛藤するのだと思います。
今回はまず「叱る」ということはどういうことなのか?を考えましょう。
よく比較されるのは「怒る」という言葉。
2つの言葉の違いは、
「叱る」→「相手の為」(指導の一環として行う)
「怒る」→「自分の為」(感情の爆発であり憂さ晴らし)
ざっくり言うとこうなると思います。
しかしここで疑問なのが、叱ることと怒ることは結果や目的が違うけど、
「プロセスの段階では混ざり合ってるのではないか?」ということです。
喜怒哀楽というようにやはり私達は犬を叱っている時に少なからず「怒り」の感情を持っているのではないでしょうか。
ちょっと一緒に考えてみましょう。例えば、
年下の部下が上司である自分に対してタメ口をきいてきたらどうしますか?
①不快感を露わにした顔で立ち去る
②毅然とした静かな口調で「その口のきき方は何だ」と諭す
③「誰に向かって口をきいている!」と激高する
あなたならどれを選びますか??(聞こえなかった振りをする、聞き流すというのはなしで!)
もちろん皆さん立場が違うのでこれが正解というのはありません。
しかしここで気付くのは、3つとも全部怒っていますね?怒りの大きさに差はあれど!
模範解答ならば②でしょうか。
「その口のきき方は何だ。失礼にあたるからやめなさい」と厳しくも優しくも指導している場面が想像できます。
①の場合も表情ですでに怒りは伝えていますし、立ち去ることで無視という社会的な罰を与えています。
勘のいい部下ならば「やってしまった・・・」とすぐに気付き、謝罪にくるでしょう。
ただ、勘の悪い部下ならばあなたが怒っていることすら気付かないで終わるかもしれません。
そして③ですが、これはかなり怒っていますね~。怒りのレベルは高いでしょう。
普通に考えるとこれはダメです。自分の為のただの感情の爆発になってしまい、指導にはならないからです。
しかし本当にそうでしょうか?
怒りにまかせて怒鳴り散らすのはもちろんダメです。
ただし、怒りのレベルを高く保ち、叱るのは良いです。むしろそうしないと理解できない者もいるということです。(犬もね)
③の「激高」の部分を「大喝」にしたらどうでしょう?
何となくOKのような感じがしますよね。不思議ですが言葉のもつニュアンスは大事です。
整理しますと、
叱るということは怒りの感情が伴うということ。
怒りの感情の大小が相手に伝わるかどうか影響すること。
注意しなければいけないのは怒りが大きすぎて自分で制御できなくなると、ただの憂さ晴らし的な感情爆発になる点です。
よく相手の嫌な部分を我慢するのはいけないといいますが、
それは怒りは生まれてはたまり続けているからです。いつかドーンッとなります・・・!(コミュニケーションが大事ですね)
さて本題の犬の正しい叱り方ですが、
まずは本当に怒ること。それを叱りに変換するのです。
「〇〇ちゃん、ダメよ~」と、本当は怒ってないけど叱ろうとはしている場面を見かけます。
世間体とかもあるので人前で怒るのは気がひけます。スマートに叱れればいいなと思ってしまいます。
しかしそれでは犬には伝わりません。怒ってないのはバレてます。(というか感情は全て読まれてる)
まずは怒りましょう。問題はどうやって表現するか?どうやって犬に伝えるかなのです。
言葉で叱るのは感情表現が豊かな人に向いている叱り方です。
しかし場合によっては(怒りレベルが低い)全く通じない叱り方に成り下がりますし、
別の怒り(しつけがうまくいかない)が加わってくるとただの激高になります。
次に、音でビックリさせる叱り方ですが3ヶ月齢くらいの子犬には通じるかもしれませんが、成犬は少々の音では懲りないでしょう。
そして音の大きさは怒りの大きさにきっと左右されることでしょう。
最後にリードやカラーを使う叱り方ですが、これは効きすぎる場合があるので下手には使えません。
言葉や音と比べて直接的な手段になるのでその効果は絶大なのですね。
以上、犬の叱り方について書きましたがどんな叱り方にも共通するのはタイミングとインパクトが重要ということです。
現行犯で3秒以内に叱る!一回で教えてあげる!
皆さんの健闘を祈ります♪
基本的には褒めて育てましょう。しかし、時には叱ることも必要です。
これはほとんど皆さん共感頂けると思います。
「褒めて育てる」と言うと、まるで叱らないのかなと思われます。逆もまた然り。
過ぎたるは及ばざるが如しのことわざ通り、偏りすぎてはいけません。
これは量的ではなく、質的な意味合いです。
9割褒めて1割叱るくらいが理想(褒めの量が多い)なのですが、褒めも叱りも同じくらい大切(質的には同等)だと考えます。
さて真の問題ですが、
「どのように褒めるか?どうやって叱るか?」です。
結局のところ・・・褒めても叱っても愛犬に通用しないから困るのですね!悩むのですね!
「何を」「何故」という部分は人それぞれなので今回は省きますが、
「どのように」の部分は基本があります。
まず、犬に初めからは言葉は通じません。(都合の良い事だけは通じるかも?)
言葉を使うのは後にとっておきましょう。
次に、態度ははっきりと示します。(笑いながら叱る、無表情で褒めるのはダメ)
喜怒哀楽を全身で表現しましょう。
最後に・・・本気でやりましょう。(根気よりも本気)
良いことか悪いことかを伝えるのに時間をかけてはいけません。
人を噛んでもいいかどうか?果たして・・・などと悩む必要はないですね。
判断に迷えば犬の心は遊びに行ってしまいます。あらかじめしつけ方針は決めておくこと。
テクニックの部分としては歩く際などは身体を使いこなすことです。
例えば、散歩で前に飛び出す犬を叱りたい場合は、飛び出す前に犬の進路を自分の足でブロックして曲がります。(足に意思を込める)
そのまま犬に迫って止まればプレッシャーを与えられます。
うまくいくかどうかはさておき、叱るということの本質は「制すること」です。
昔のように棒でひっぱたくとか、怒鳴りつけることだけが叱ることではありません。歩き方でも制することは可能!
これに対して、褒めるということの本質は「感謝」です。
「サンキュー」と愛犬に言いたくなればそれはもうすでに褒めです。(毎日言ってあげましょう)
結論としては、「どのように感謝を伝えるか?どうやって制するか?」が重要ということです。
基本を踏まえた上で、固定観念にとらわれずに創意工夫してみて下さいね♪